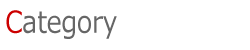歴史あるお風呂『大湯屋』『鉄湯船』初の特別公開 @東大寺

奈良市・東大寺で、鎌倉時代に東大寺復興に尽力した「重源上人」ゆかりの、入浴施設『大湯屋』が初の一般公開が行われています(2017年7月1日~31日)。内部には唐破風の小屋があり、その中心には直径2メートルを超える巨大な『鉄湯船』が。初めて拝見できて興奮しました!あわせて重源上人坐像を祀る「俊乗堂」も特別公開中ですのでぜひ!
JR西日本「ちょこっと関西歴史たび」で
華厳宗の大本山であり、奈良の大仏様がおわすお寺『東大寺』。7月1日から1ヶ月間、普段は一般公開していない「大湯屋(おおゆや)」と、通常は年に二度のみ御開扉される「俊乗堂(しゅんじょうどう)」が特別公開されています。
この大湯屋は、入浴施設です。源平の合戦の際の南都焼討によって焼失してしまいましたが、鎌倉時代の東大寺復興を主導した「重源上人(ちょうげんしょうにん)」(Wikipedia)によって再建されました。
内部にもうひとつの小さな覆屋が建っていたり、外からではわからなかった内部の様子が見られて、とても興味深かったです!
今回の特別公開は、JR西日本の2017年7月~9月のキャンペーン「ちょこっと関西歴史たび 世界遺産 東大寺」によるもの。8月以降も「東大寺大仏縁起絵巻」(重文)の特別公開などが行われますので要チェックです!
東大寺の「大湯屋」を、二月堂から大仏殿方面への道から見たところ。普段は一般公開していませんし、東大寺の巨大な「鐘楼(大鐘)」の南側の段差の下と、ちょっとわかりづらい場所にあるため、その存在に気づいていない方もいらっしゃるかもしれませんね
扉が開け放たれた東大寺「大湯屋」。一般公開されるのが初めてのことですから、とても貴重な光景です。ちなみに、拝観料は「俊乗堂」「大湯屋」共通になっていて、支払いは俊乗堂の前で行います。先に俊乗堂に参拝するルートがスムーズです
大湯屋の内部には唐破風の小屋が
■大湯屋(重要文化財)
・湯屋が初めて建てられた時期は、伽藍が建立まで遡ると想像される。
・1180年の兵火で焼失。重源上人によって東大寺の再建に関わる人たちのために再建された。
・その後は僧侶たち、参拝者も使用したとか。
・鎌倉時代の1239年、室町時代の1408年に改修されている。
・東西八間、南北五間。大仏様と禅宗様を用いたすっきりした意匠。
・内部の唐破風がついた建物は、江戸時代に造られたもの。
・大きな法会の前に東大寺僧侶が集まり「蜂起の儀」が行われている。
・いつまで入浴施設として使われていたのかは不明。
東大寺・大湯屋に入ってすぐ。お堂の外陣・内陣のように仕切られていて、さらに奥には大きな土間があり、3分割された形になっています
そして、内陣にあたる場所には、曲線が美しい「唐破風(からはふ)」を用いた覆屋が建っています。これは江戸時代に建てられたもの。建物の中に建物がある、二重構造のような感じですね。この小屋を作ることで、蒸気をこもらせて蒸し風呂のような効果を狙ったのでしょうか?詳細は不明です
見事な唐破風。ガイドさんの説明によると、唐破風という建築様式が用いられ始めたのが、戦国時代末~江戸時代にかけてのこと。鎌倉時代の建物の中に、江戸時代の様式が取り入れられたことになります。近代の銭湯建築には、これと同様に唐破風を用いたものが多いのですが、東大寺の影響もあるのでは……とのことでした
中央には直径2m強の巨大な「鉄湯船」
■鉄湯船(重要文化財)
・鉄製。鋳造。2000~3000リットル入るらしい。
・重源上人の『南無阿弥陀仏作善集』に「大湯屋一宇。在鉄湯船。」と記されている。
・外面に鋳物師師・草部是助が1197年(建久8)に造ったとの銘文が刻まれている。
・大仏殿再建のはじめ頃には、屋内に大釜2口が置かれていたが、その後で鉄湯船にされた。
・形は扁平で、中央に水抜きの穴が開いている。地面の下には排水溝も。
・隣の土間に釜が設置され、湧いたお湯がほぼ自動的に供給されていたようだ。
・土間にすのこを敷いて、かけ湯方式で使用されたと考えられている。
唐破風の覆屋の下には、堂々と巨大な「鉄湯船」(重要文化財)があります。口径約2.3m・高さ約80cmで、容量は2000~3000リットルほどだとか。現在は井桁で持ち上がっていますが、当時は地面に埋められる形でした。周りの固められた土間部分にすのこを置き、そこに布(後の風呂敷)を敷いて、かけ湯して使っていたそうです
鉄湯船の表面には銘が入っていますが、遠目にはよく見えません
鉄湯船の銘文の解説。「年中行事記」に記された文と照合できるようです(7月30日まで東大寺ミュージアムに展示中)。ここに「豊後権守」として登場するのが、重源上人に命じられた鋳物師師「草部是助」のこと
その背後には大きな土間があります。ここに2口の大釜を置いて湯を沸かし、鉄湯船へ樋(とい)をわたして、半自動的にお湯を供給できるようにしていたのではないか、とのことでした
土間の天井を見上げると、煙出しが設けてあります。お湯を沸かすためにもうもうと煙が上がっていたでしょうし、湯気もすごかったのでしょう。当時の様子が想像できますね
鉄湯船の底には水を抜くための穴が開いているそうです(残念ながら見えません)。ちなみに、現在の銭湯のように、大きな湯船に多人数で入る習慣が始まったのは、江戸時代くらいのことだとか。浮世絵などにも描かれていますね
大仏様などを用いた建築も注目
大湯屋の建築は、重源上人が関わった他の建物と同時代のものらしく、大仏様と禅宗様を用いたすっきりした作りです。細部まで注目してみるととてもおもしろいですよ!
唐破風の建物を横から見たところ
なお、東大寺・大湯屋のすぐ脇には、東大寺の田んぼがあります。田植え直後のこの時期は、こんな美しい光景が見られますので、ぜひ注目してみてください
余談ですが、こちらは興福寺の「大湯屋」(重要文化財)です。奈良時代から設けられていて、現在の建物は室町時代のもの。蒸し風呂にしたり入浴したりして使っていたとか。こちらも通常は非公開なので、外側から内部の様子を想像してみてください!
重源上人坐像など「俊乗堂」の仏さまも
大湯屋とあわせて特別公開されている「俊乗堂」。こちらには慶派仏師によるリアルな造形の「俊乗坊重源上人坐像」(国宝)がおわし、その両脇に快慶作の「阿弥陀如来立像」(重文)、美しい「愛染明王像」(重文)が祀られています。毎年、7月5日の「俊乗忌」、12月16日の「良弁忌」の日にしか参拝できませんので、1ヶ月間も御開扉される今回は、本当に貴重です。ぜひお参りください!
■ちょこっと関西歴史たび 世界遺産 東大寺
HP: http://www.jr-odekake.net/navi/rekishi_tabi_todaiji/
●特別公開「俊乗堂」「大湯屋」
・期間: 2017年7月1日~31日 10:00~16:00
・拝観料(共通): 大人600円、小学生300円
●特別公開 重要文化財「東大寺大仏縁起絵巻」
・期間: 上巻 8月1日~20日、中巻 8月22日~9月10日、下巻 9月11日~30日
・入館料: 大人500円、小学生300円 ※大仏殿との共通割引券(大人800円、小学生400円)
※その他、期間中の週末を中心に「境内ガイドウォーク」「特別法話」なども開催されます。
■東大寺
HP: http://www.todaiji.or.jp/
住所: 奈良県奈良市雑司町406-1
電話: 0742-22-5511
宗派: 華厳宗大本山
本尊: 盧舎那仏(国宝)
創建: 8世紀前半
開基: 聖武天皇
拝観料: 大仏殿-600円、法華堂-600円、戒壇院-600円、東大寺ミュージアム-600円など
拝観時間: 4月~10月 7:30-17:30、11月~3月 8:00-17:00
駐車場: 近隣に有料駐車場あり(一日1,000円程度)
アクセス: JR奈良駅・近鉄奈良駅より、市内循環バス「春日大社大仏殿前」下車、徒歩5分
■参考にさせていただきました
重源ゆかり大湯屋初公開 東大寺、7月から「歴史たび」 奈良 - 産経ニュース
重源 - Wikipedia
銭湯 - Wikipedia
■関連する記事