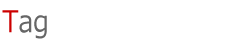寺社勢力の中世―無縁・有縁・移民 (ちくま新書)
公家と武士に匹敵する力を持った中世の寺社。その成立過程を解説した良書
日本の中世を考える際に、どうしても「公家」と「武士」の勢力争いに注目されがちですが、本書ではそれらと匹敵するほど大きな勢力を誇った「寺社」について、主に比叡山と京都の関係性などから考察しています(もちろん、南都の寺社についても触れられています)。
戦闘に参加する「僧兵」が闊歩し、不満があれば神の依代を掲げての「強訴」を行うなど、今の時代の寺社の姿から考えるとあまりにも異質に思えます。
寺社の境内はある意味では独立都市のように機能しており、逃亡してきた貧者たちが居着いても排除されることはありませんでした。悪人であろうが社会的な敗者であろうが、寺社に逃げ込めば少なくとも追手から逃れることができ、筆者はそれを外から隔絶されたイメージで「無縁の場」とし、これをキーワードに読み解いています。
説明文:「日本文明の大半は中世の寺院にその源を持つ。最先端の枝術、軍事力、経済力など、中世寺社勢力の強大さは幕府や朝廷を凌駕するものだ。しかも、この寺社世界は、国家の論理、有縁の絆を断ち切る「無縁の場」であった。ここに流れ込む移民たちは、自由を享受したかもしれないが、そこは弱肉強食のジャングルでもあったのだ。リアルタイムの史料だけを使って、中世日本を生々しく再現する。」
平安時代の京都には、国司の悪政などによって流入民が多く集まり、治安が悪化していました。そういった人々が駆け込むのが寺社の広大な境内でした。とはいえ、慈悲深く食料の施しがあったりするのではなく、そこにいれば排除されない、という程度のものだったそうです。
当時の京都は、比叡山の門前町といった感もあり、経済や流通、金融の大きな部分を牛耳っていました。境内でも商業・工業活動が活発で、ここに来れば職があり、最新のスキルも学べるため、次第に僧侶以外の者の比率が増えていきます。
寺社内のヒエラルキーもはっきりしていて、貴族や武士などの出身で宗教的な研鑽を行う「学侶」を筆頭に、雑役を務める下級僧侶「行人(堂衆)」が多数おり、さらにその下に定住地を持たず各地を遊行するが存在しました。現在と比べて、団体としての規模が大きすぎるため、いわゆる今イメージされる僧侶という人の割合は極端に少なかったのです。
現代の寺社を見てきているだけに、そのイメージに引きづられてしまいがちですが、本書ではそういった思い込みを払拭し、リアルな中世の寺社の姿を描いています。とても興味深い内容で、また必ず読み直したいと思います。
また、僧兵などについては、以前読んだ『僧兵=祈りと暴力の力 (講談社選書メチエ)』がとても興味深かったです。決して読みやすい本ではありませんが、興味のあるかたは合わせてどうぞ。