
唐招提寺『礼堂(らいどう)』特別公開@奈良うまし冬めぐり

2013年冬に開催された『奈良 うまし冬めぐり』に特別にお誘いいただいて、念願だった「唐招提寺 礼堂(らいどう)」の特別公開に参加させていただきました。堂内には清涼寺式の釈迦如来像と、美しい細工を施した舎利塔が安置されていました。古建築好きな私には夢のような時間でした!
『奈良うまし冬めぐり』に参加させて頂きました
2013年1月12日~2月24日まで、奈良にご宿泊いただいたお客さまへのおもてなしとして開催されていた『奈良 うまし冬めぐり』。今回は特別にお誘いいただいて、最終日に「唐招提寺」礼堂(らいどう)の特別公開に参加させていただきました(詳しくはこちら。すでに終了しています)。
『奈良うまし冬めぐり』の企画への参加は、すべて事前予約が必要です。現地へ着くと、唐招提寺では入口となる「南大門」脇の受付で、事前予約してある旨を申し出て、目立つところに貼るシールなどをいただきます。あとは所定の時間になったらご案内が始まって…というだけですから、難しいことは何もありません。申し込みがやや面倒に感じられるかもしれませんが、それだけで特別な体験ができるんですから素晴らしいですね!
※2013年の『奈良うまし冬めぐり』キャンペーンは終了しましたが、2014年の冬も開催予定だそうです。国宝の塔、特別なお庭や建物の中が拝見できたり、僧侶や神職の方からご案内いただきながら参拝できたりと、とても豪華な内容でしたので、来年も期待したいですね!

『奈良うまし冬めぐり』の受付は、唐招提寺の「南大門」前にありました。事前申し込みをした方は、ここで受付を済ませてから入場します
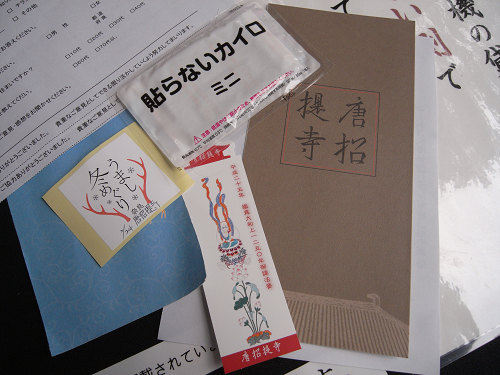
受付の際にいただいたものたち。パンフレット・特製しおり・ミニカイロ・参加者が目立つところに貼っておくシールなどです。寒い真冬ですから、簡易カイロをご用意いただいているのは嬉しいですね。なお、平成25年は「鑑真大和上1250年御諱法要」が催され、秋には「御影堂特別開扉」も予定されています

時間になったら、特別なおもてなしが始まります。ボランティアの方などのご協力もあり、僧侶の方に特別な法話を聞かせていただけました
僧侶の方のご説明付きでのお参りは楽しい!
この日参加した唐招提寺は「通常非公開の礼堂を特別公開」というおもてなしをご用意くださっていました。
この日の参加者は、私たちを含めて10名ほどでした。唐招提寺のお若い僧侶の方が参加者をご案内してくださるのですが、まずは本堂を前にして唐招提寺の縁起や鑑真和上のお話から、歴史・建築物・祀られている仏さまなど、本当に丁寧にご説明していただけます。真冬の薄曇りの一日でとても寒かったのですが、寒さも忘れて聞き惚れました(笑)
私自身、唐招提寺には何度もお詣りしていますし、ネットで調べたり本を読んだりして情報を集めてきました。普通の方と比べればそれなりに詳しいと思います。
しかし、実際に天平時代に建てられた巨大な「金堂(国宝)」を目の前に、また金堂に安置された、廬舎那仏坐像・千手観音立像・薬師如来立像の三尊像を拝しながら、僧侶の方からご説明いただけると、よりリアルに感じられるんですよね。
「千手観音像は木心乾漆像ですが、重さは1,600kgもあります」と聞くと、自宅で仏像本を読んでいるのとは理解度が全く違います。本で読んでもすぐ忘れてしまいますが、その迫力がリアルに感じられてちゃんと記憶に残るんですね。本当にありがたいことです!

まずは金堂を前にして、鑑真和上のお話や唐招提寺の歴史などを伺います

続いて金堂の前に移動し、巨大な三尊像などについて詳しくお話を伺いました。「この柱も根元の部分から根腐れていくので、下から継いでいきます」というご説明も、実物を目の前にして聞いているとより分かりやすいですね
「礼堂」は南北19間(約35メートル)もあります
金堂前でご説明を伺った後は、いよいよ通常は非公開の「礼堂(らいどう)」(重要文化財)の中へ入ります。堂内へ入るのはもちろん初めてのことでしたから、それだけで感動でした!
この礼堂は、隣接する2階建ての「鼓楼(国宝)」に安置された仏舎利「金亀舎利塔(国宝)」を礼拝するためのお堂です。もとは僧坊だったものを、1283年に改築したとか。南北19間(約35メートル)もある細長い建物で、南側8間が今回拝見した「礼堂」に、北側10間が「東室」に。その間の1間は「馬道(めどう)」と呼ばれる通路になっています。
ちなみに、唐招提寺の唐招提寺の伽藍配置を見てもやや分かりづらいのですが、中央に金堂が、その北側に講堂が建っていて、その間の東西に対になるように「鼓楼」と「鐘楼」があります。
もちろん、東側に建つ「礼堂」にも、西側に対となる「食堂(じきどう)」が建っていました。これは藤原仲麻呂が寄進したというものでしたが、残念ながら現存していません。その形状は分かりませんが、こんな細長い建物がもう一つあったかと想像するだけで面白いですね。

唐招提寺の金堂に向かって右手奥に建っている「礼堂(らいどう)」。通常は非公開ですが、『奈良うまし冬めぐり』では特別に公開してくださいました。向かって左に見切れているのが「鼓楼(ころう)」です。毎年5月19日の「中興忌梵網会」(通称:うちわまき)では、ここから1,500本のうちわが撒かれていたことで知られています

金堂(向かって右手)と講堂の間から見た図。正面は鼓楼で、その向こう側が礼堂です

さらに別アングルから。左手が礼堂です。真ん中の通り抜けできるところ(「馬通(めどう)」といいます)で二分されています。中には入れませんが、縁側の部分に腰掛けて休憩できたりします。重要文化財の建築物なのに身近ですね!
中央には「日供舎利塔」と「釈迦如来立像」
礼堂の内部にはストーブもついていましたが、普段はたくさんの人が立ち入るようなお堂ではありませんので、空気がヒンヤリとしていました。
礼堂に入ると、正面に涅槃図などが祀られています。まずは僧侶の方が法要前に1番太鼓・2番太鼓を鳴らします。最初は軽い音で、次第に腹に響くようなずっしりとした音へ変わっていきます。その後、梵網経(ぼんもうきょう)の一部を読経していただきました。
現在でも、鑑真和上の月命日に当たる毎月6日、覚盛(かくじょう)上人の月命日19日には、ここでこうして梵網経を唱えていらっしゃるそうです。
礼堂の内部は写真撮影などはできませんので、細かい目にその様子を書きだしておきます。
●礼堂の内部は、周囲が畳敷き、中央部分の5間分くらいが板敷きで、内陣のような作りになっています。東側には柱2本、西側(鼓楼側)は柱5本が建っていて、さらに礼堂の東側は蔀戸(しとみど。上に持ち上がる形の扉)になっていますから、東側から礼堂を通して西側の鼓楼を拝する形だったようです。
●天井は格天井。創建当初のものではなく、僧坊から礼堂へ改築された際に変えられたものかも?
●内陣には、南側から順番に、江戸時代の「涅槃図」、鎌倉時代の「日供舎利塔(にくしゃりとう)」(重文)、礼堂のご本尊「釈迦如来立像(重文)」と並びます。仏さまは南向きに立っていらっしゃるので、南から入った参拝者と涅槃図と仏舎利を間にして向き合う形になります。
●仏舎利「日供舎利塔」は、蓮弁の上に金銅製の火炎とガラス容器があり、鑑真和上が持参された「如来舎利三千粒(にょらいしゃりさんぜんりゅう)」から分けられた数十粒が収められています。日々供養されるため「日供(にく)」と名付けられたとか。
●お厨子の赤い緞帳の向こうに「釈迦如来立像(重文)」がいらっしゃいます。衣紋が細かなドレープ状で、縄状に結われた髪型が特徴の、いわゆる「清涼寺式」よ呼ばれる如来像で、像高は166cm。凛とした美しいお方でした。
(日供舎利塔・釈迦如来立像は「礼堂」ページに画像があります)

東側から見た「礼堂」の様子。南側の礼堂部分は8間で、中央の3間は上に持ち上がる「蔀戸(しとみど)」になっていて、石段も設けられています。ここを開け放って外から内部の仏舎利と、隣接する鼓楼を拝んだのでしょう

礼堂の中央にある「馬通(めどう)」。これを境にして「礼堂」と「東室」に分かれます。別の建物にせず、あえてひとつの長い建物にしたことにも、何らかの理由があるんでしょうね

唐招提寺・礼堂の「閼伽井屋(あかいや)」。もとは仏さまに捧げる水(閼伽)を汲む井戸を覆ったもので、お堂の裏手などに配置されることが多いです
入れなかった「東室」は修学旅行生も上がれる?
ちなみに、礼堂の北側10間分の「東室」ですが、こちらには入口の上に名札のようなものがついているそうです。教えていただいて初めて気づきました!
なお、今回はこの東室には入れませんでしたが、話によると、修学旅行生などの団体さんはここで食事をすることもあるとか!そういうものなんですね(笑)。いつかそんなチャンスが来ることを待ちたいと思います。

唐招提寺・礼堂の「東室」部分。10間もある長い建物です

東室には3ヶ所の扉があり、それぞれに表札のようなものがついています。文字を読み取っていってみてください!
10月21日~23日は礼堂が特別公開されます
今回、礼堂で上がらせていただきましたが、決して華美ではありませんが、しっかりとした祈りの空間になっていることが伝わって来ました。古い寺院建築が好きな私にとっては、念願が叶って本当に嬉しかったですね。
この礼堂では、1月15日の「大般若経転読法要」、2月15日の「涅槃会」、大晦日の「修正会」など、年に4回の法要が営まれています。中でも、毎年10月21日~23日の3日間催される「釈迦念仏会」の際は、一般の参拝客も礼堂をお詣りできるそうです。
釈迦念仏会とは、鎌倉時代の高僧「解脱上人貞慶」が始めた800年もの歴史を持つ法要で、お釈迦さまの宝号「南無釈迦牟尼仏(なむしゃかむにぶつ)」を唱えます。通常はお隣の「鼓楼」に収められている仏舎利「金亀舎利塔(国宝)」が礼堂へ移され、釈迦如来立像とともに特別公開されますので、ぜひこの日にお詣りしてみてください!

<オマケ>唐招提寺・金堂の「隅鬼(すみおに)」その1。軒を支えている小さな鬼の姿が見えます。絵葉書になっているほどの人気者です!

<オマケ>唐招提寺・金堂の「隅鬼(すみおに)」その2
■唐招提寺
HP: http://www.toshodaiji.jp/
住所: 奈良県奈良市五条町13-46
電話: 0742-33-7900
宗派: 律宗(総本山)
本尊: 廬舎那仏(国宝)
創建: 759年
開基: 鑑真
拝観料: 600円(新宝蔵は別途100円)
拝観時間: 8:30 - 17:00
駐車場: 有料駐車場あり(500円)
アクセス: 近鉄橿原線「西ノ京駅」から徒歩10分
※実際にお詣りしたのは「2013年2月24日」でした
■関連する記事
















