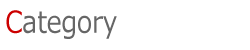超絶技巧!国宝3点が揃った『糸のみほとけ』@奈良国立博物館

奈良国立博物館で開催中の『糸のみほとけ』展(7月14日~8月26日)。刺繡や綴織といった技法を用いて仏の姿を表した作品が多数集まり、「天寿国繡帳」「綴織當麻曼荼羅」「刺繡釈迦如来説法図」の国宝3点が勢ぞろいするという豪華な内容です。“糸のみほとけ”という世界の広がりに驚き、その技術のすごさに驚き、人々の思いに驚き。感動しました!
『糸のみほとけ』展の見どころ
●綴織や刺繡の仏の像にこんなバリエーションが!
●「天寿国繍帳」が(ガラス越しに)間近で!
●「刺繡釈迦如来説法図」が細密&超絶技巧!
●織物だけに立体的に見えたり質感がすごい!
●縫い方が多彩!手法が解説されていて面白い!
●布モノや手芸好きな方は楽しめるはず。
国宝の“糸のみほとけ”3点が一堂に!
奈良国立博物館で開催中の『修理完成記念特別展 糸のみほとけ ─国宝 綴織當麻曼荼羅と繍仏─』展。刺繡(ししゅう)や綴織(つづれおり)といった技法を用いて、絵画ではなく「糸」で仏の姿を表した作品が多数集められた企画展です。
その展示の予告を聞いた際に、「あれ?そんなに作品があったっけ?」と思ったことを覚えています。
こうした作品の例として、まず思い浮かぶのは、飛鳥時代(7世紀)に作られた、国宝「天寿国繡帳(てんじゅこくしゅうちょう)」(中宮寺蔵)でしょう。聖徳太子が亡くなった際に、往生後の世界を刺繡させた作品です。
そして、サブタイトルにもなっている、国宝「綴織當麻曼荼羅(つづれおりたいままんだら)」(當麻寺蔵)は、奈良時代(8世紀)に中将姫(ちゅうじょうひめ)が蓮糸を使って一晩で織り上げたと伝わる、約4m四方もある巨大な作品です。
私の知識ではこんな程度ですが、かつて大寺院では、仏像の造像に劣らないほど重要視され、糸のみほとけが本尊として祀られていたのだそうです。
解説にありましたが、奈良時代の東大寺大仏殿には、巨大な繍仏作品が掛けられていたとか。その大きさは、なんと高さ16m!大仏さまと変わらないほどのサイズだったというのですから驚きます(※現存していません)。
しかし、会場を回ってみると、製法や時代ごとにさまざまなバリエーションがあり、いずれも“超絶技巧”というべき技術を駆使して制作されていることがわかります。会場を巡りながら、「おぉ、すごい!」と何度口から出たことか。他の企画展と比較すると、決して派手さはありませんが、新たな気付きが多く、見応えたっぷりでした。
奈良国立博物館『修理完成記念特別展 糸のみほとけ ─国宝 綴織當麻曼荼羅と繍仏─』展のチラシ表面。「綴織當麻曼荼羅」「天寿国繍帳」「刺繡釈迦如来説法図」という、国宝に指定されている糸のみほとけ3点が一堂に会します
チラシ裏面。前期後期の入れ替えがありますが、約140点もの糸のみほとけと関連する資料などが展示されます
奈良国立博物館の前の池では、ちょうど蓮の花が開花していました。午後には花が閉じてしまいますので、早めの時間帯にご覧ください
感動!中宮寺「天寿国繍帳」が間近に!
国宝「天寿国繍帳(てんじゅこくしゅうちょう)」中宮寺蔵
(※以下、展示品の画像はすべて「糸のみほとけ|奈良国立博物館」より引用)
会場に入ると、真っ先に展示されていたのがこちら。これまでに何度か実物を拝見してきましたが、今回はガラスを挟んで数十センチの距離でじっくりと拝見できます!見れば見るほど美しく、愛らしく、聖徳太子への純粋な追慕の思いが伝わってくるようでした。
間近で見るとはっきりわかりますが、刺繡糸の美しい部分と、茶色に退色してしまった部分があります。前者が制作された飛鳥時代のもの、後者が鎌倉時代に補修されたもの。古い時代のもののほうがより丁寧に作られていて、美しいまま遺されているそうです。
図中の文字が描かれた亀は、もともと百体あって、計四百文字の銘文が刺繡されていたとか。その残欠なども展示されています。現在の姿で完成形のような印象でしたが、さらにこの世界は広がっていたんですね。驚きでした!
「綴織當麻曼荼羅」のすごさ体感できます
国宝「綴織當麻曼荼羅(つづれおりたいままんだら)」當麻寺蔵
奈良時代(8世紀)に中将姫が蓮糸を使って一晩で織り上げたと伝わるもの。葛城市の古刹・當麻寺(たいまでら)に伝わる約4m四方もある巨大な作品です。
4年がかりの修理が終わったばかりですが、かなり劣化が進んでいて、図像はそれほどよく見えません。そのためこれまで「糸で綴織されたものだ」と実感しづらく、どちらかというと古い絵画作品のようなものとして認識していました。
しかし、今回の企画展で、その一部を復元したものを見たり、他の刺繍作品を拝見することで、この巨大な曼荼羅を細い糸の一本一本を重ねていくことで織り上げたことを改めて認識できました。
綴織當麻曼荼羅 部分復元模造
会場には、當麻曼荼羅の一部を、京都・川島織物セルコンさんが復元したものも展示されていました。その色鮮やかなこと!目を凝らしてみると、ひと針ずつ丁寧に織られていることがわかって、気が遠くなります。
復元品は、わずか幅23cm×丈19cmですが、これを織るのに約40日もかかったとか。約4m四方もある當麻曼荼羅を織るには8年(!)もかかる計算になるそうです。そう考えるとますますすごい!
「刺繡當麻曼荼羅(ししゅうたいままんだら)」京都・真正極楽寺蔵
江戸時代になってから、綴織當麻曼荼羅と同じサイズで制作されたもの。その大きさと美しさに圧倒されます。江戸時代の刺繍技術が用いられたり、刺繡ではなく彩絵されていたりと、当時の新しい技術も用いられているとか。當麻曼荼羅の内容が理解しやすいですので、ぜひじっくりと鑑賞してみてください。
国宝「刺繡釈迦如来説法図」の美しさ!
国宝「刺繡釈迦如来説法図(ししゅうしゃかにょらいせっぽうず)」奈良国立博物館蔵
8世紀のもので、縦211.0cm×横160.4cmという大きなもの。こちらも4年間に及ぶ修理が終わったばかりということで、今回初めて拝見しましたが、その精密さに驚きました。
見る角度や距離によって、まったく印象が違ってきます。絵画作品だと「近づいてみたら意外と粗いな」と感じることがあったりしますが、こちらは遠くからでも緻密さが感じられ、近づくにつれてそれがより鮮明になっていくイメージ。作品の中にまた別の小宇宙があって、そこへ飛び込んでいくような錯覚にすら陥りました。じっくり時間をかけて鑑賞してみてください!
重要文化財「刺繡阿弥陀名号(ししゅうあみだみょうごう)福島・阿弥陀寺蔵
鎌倉時代以降にまた盛んに作られるようになった刺繡の作品。當麻曼荼羅を織ったとされる中将姫に対する信仰の高まりにあわせ、極楽往生を願う人々が阿弥陀三尊来迎図や種子阿弥陀三尊図を作成したそうです。
その特徴は、画中の黒い部分(この作品なら文字の部分)に髪の毛を用いて刺繍していること。こうすることで髪の持ち主が極楽へ召されることを願ったのでしょう。こうした人々の念がこもった作品が多数展示されています。
また、時代がくだるにつれ、刺繍で描く部分と、絵の具で彩色する部分を組み合わせるなど、より洗練された仏画技法を用いたものなども作られたようです。そういった変遷が見られるのも面白かったですね。
[感想1] 絵画とは違った魅力があります
洋画が中心の展覧会などでは、「実際に見てみると筆跡などがリアルに感じられて、画集で見ているのと迫力が違う!」ということがあります。絵画制作の経験が乏しいと、油絵の具がキャンパスから盛り上がっていることすら想像できませんから、単なる平面ではないことに驚いたりするものです。
今回拝見した糸のみほとけたちの「写真と全然違う!」感は、その比ではありません。とにかくものすごい超絶技巧(にしか見えない細かさ)が用いられていることがわかります。
美しい絵画作品かと思いきや、よくよく目を凝らして見ると、それが織り物であることがわかったりします。縫い重ねることで立体的に見えたり、左右や上下からなど見る角度を変えることで色合いがまったく変わったリ。
こうした糸のみほとけたちは、亡くなった方への供養のため、または極楽浄土へ行くため、ひと針ずつ祈りをこめて織られます。絵の具で描いたほうが圧倒的に早くて安いであろうに、あえてこの手法を選んでいるのでしょう。人々の思いが伝わってくるようでした。
[感想2] 編み物や縫い物好きな方は必見!
また、本展覧会では、刺繍の技法なども丁寧に解説されているのが特徴です。
展示している作品では、刺し繡(さしぬい)だったり、鎖繡(くさりぬい)相良繡(さがらぬい)など、部分ごとに異なる技法を用いていますが、それらを館内で解説映像を流したり、図にして掲示してあったりします。
私のような中年男となると、編み物や縫い物の経験はほぼありません(家庭科の授業で刺繍をやったことがある程度です)。このため、やはりピンと来づらい感はあるのですが、ウチの奥さんは布モノも大好きで、編み物も縫い物も経験していますので、この企画はよりリアルに感じられたようです。
語弊のある言い方かもしれませんが、“手芸好きな女性であればより楽しめる”内容だといえるかもしれません。ぜひ足を運んでみてください!
会場内の記念撮影スポット。手前のアップリケ風のものと背後のカメ柄は、いずれも「天寿国繍帳」のもの。どんなポーズをとれば似合うのか悩みそうですね(笑)
■奈良国立博物館
HP: http://www.narahaku.go.jp/index.html
住所: 奈良県奈良市登大路町50番地
電話: 050-5542-8600(NTTハローダイヤル)
●修理完成記念特別展 糸のみほとけ ─国宝 綴織當麻曼荼羅と繍仏─
HP: https://www.narahaku.go.jp/exhibition/2018toku/ito/ito_index.html
会期: 2018年7月14日(土)~8月26日(日)
休館日: 毎週月曜日 ※7月16日、8月13日は開館
開館時間: 9:30 - 18:00(金土と8月5日~15日は19時まで)
拝観料: 大人 1,500円、大学生・高校生 1,000円、中学生・小学生 500円
●公開講座
・7月21日(土)「国宝綴織當麻曼荼羅 ―― その図様と意義」大西磨希子氏 (佛教大学教授)
・8月4日(土)「繡仏の世界 ―― 刺繡釈迦如来説法図(奈良国立博物館蔵)を中心に」
内藤栄氏(奈良国立博物館学芸部長)
・8月11日(土)「飛鳥から奈良時代における刺繡と金糸の技法の変遷」沢田むつ代氏 (東京国立博物館客員研究員)
●関連イベント
・7月29日(日)親子向けワークショップ「織ってみよう!糸のみほとけ」
・8月5日(日)大人向けワークショップ「天寿国繡帳の繡い方を体験しよう!」
■参考にさせていただきました
奈良国立博物館 特別展「糸のみほとけ」 - YouTube
※実際に拝見したのは「2018年7月17日」でした。